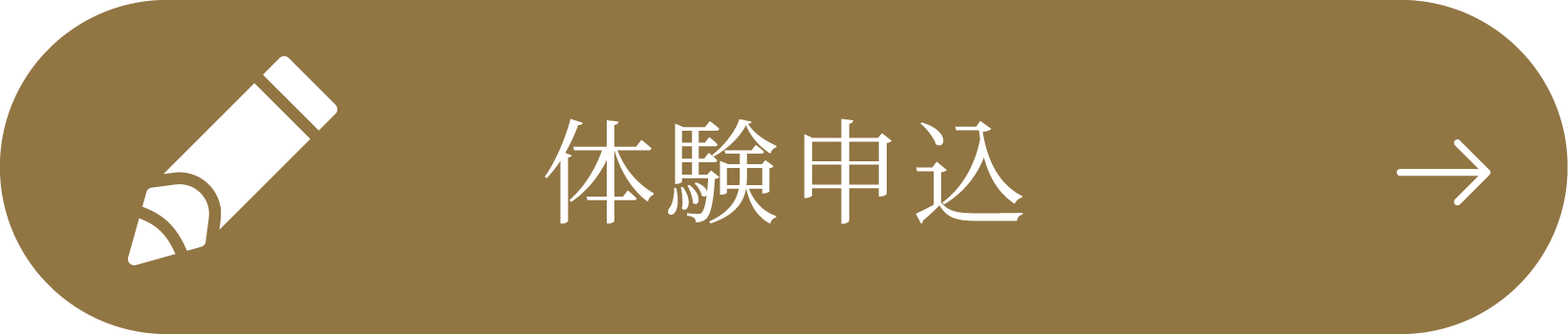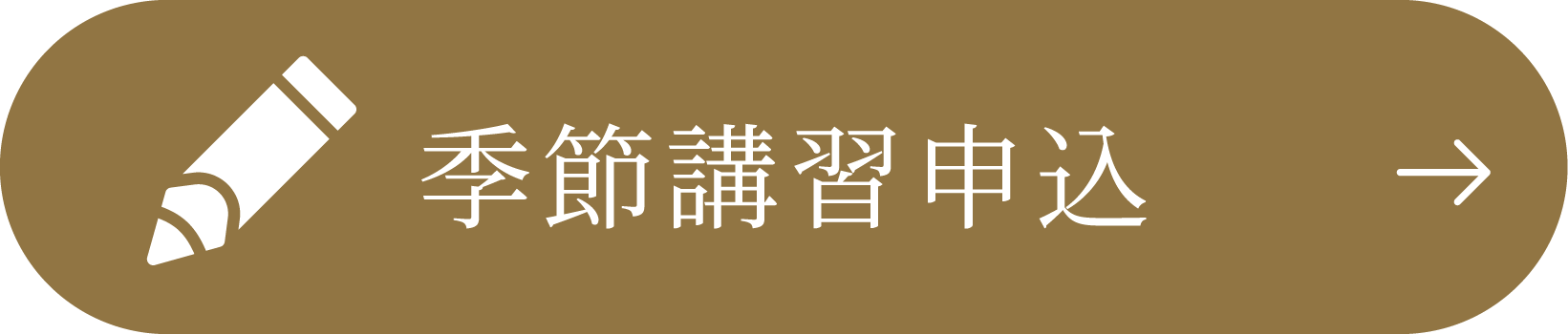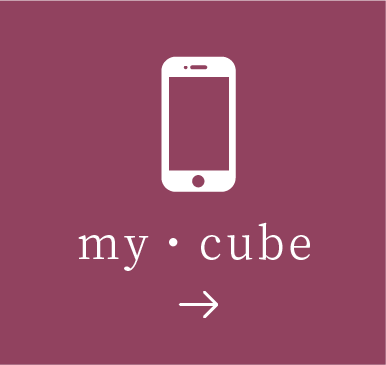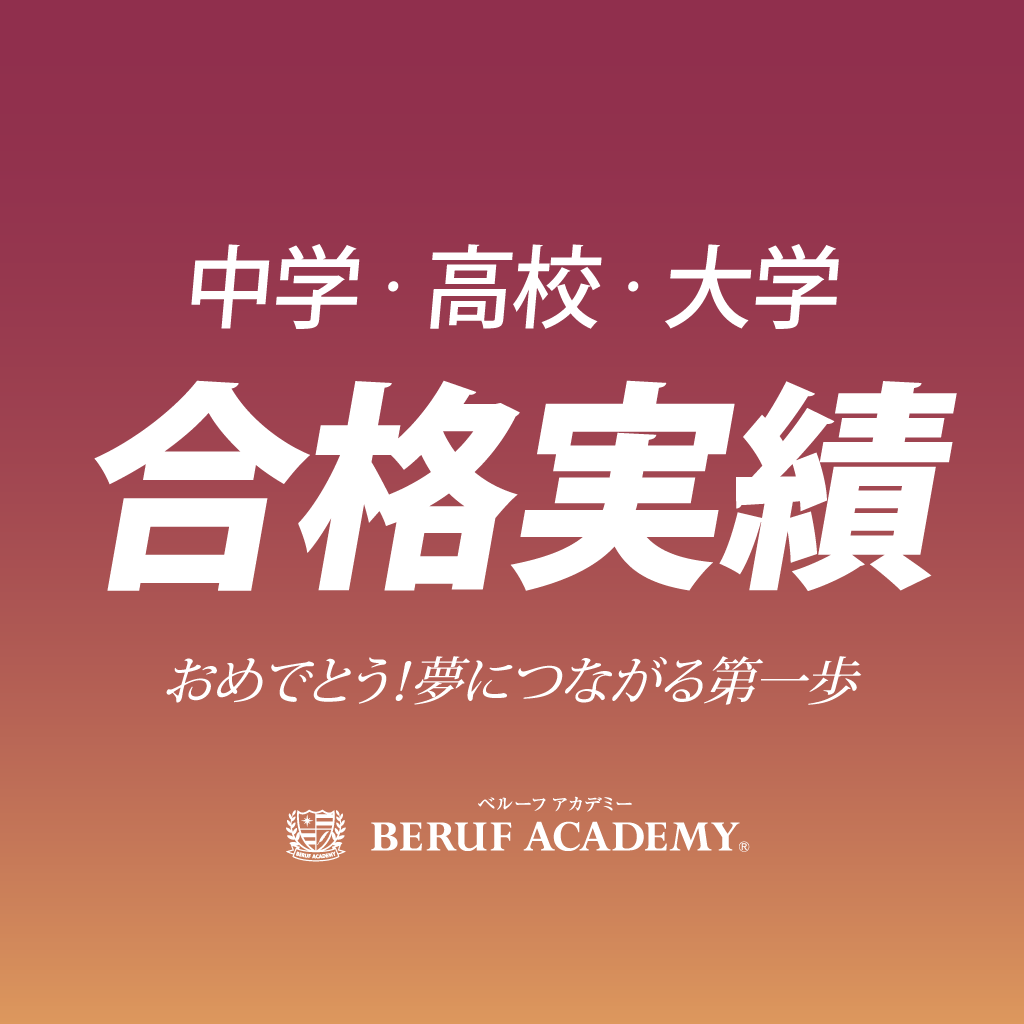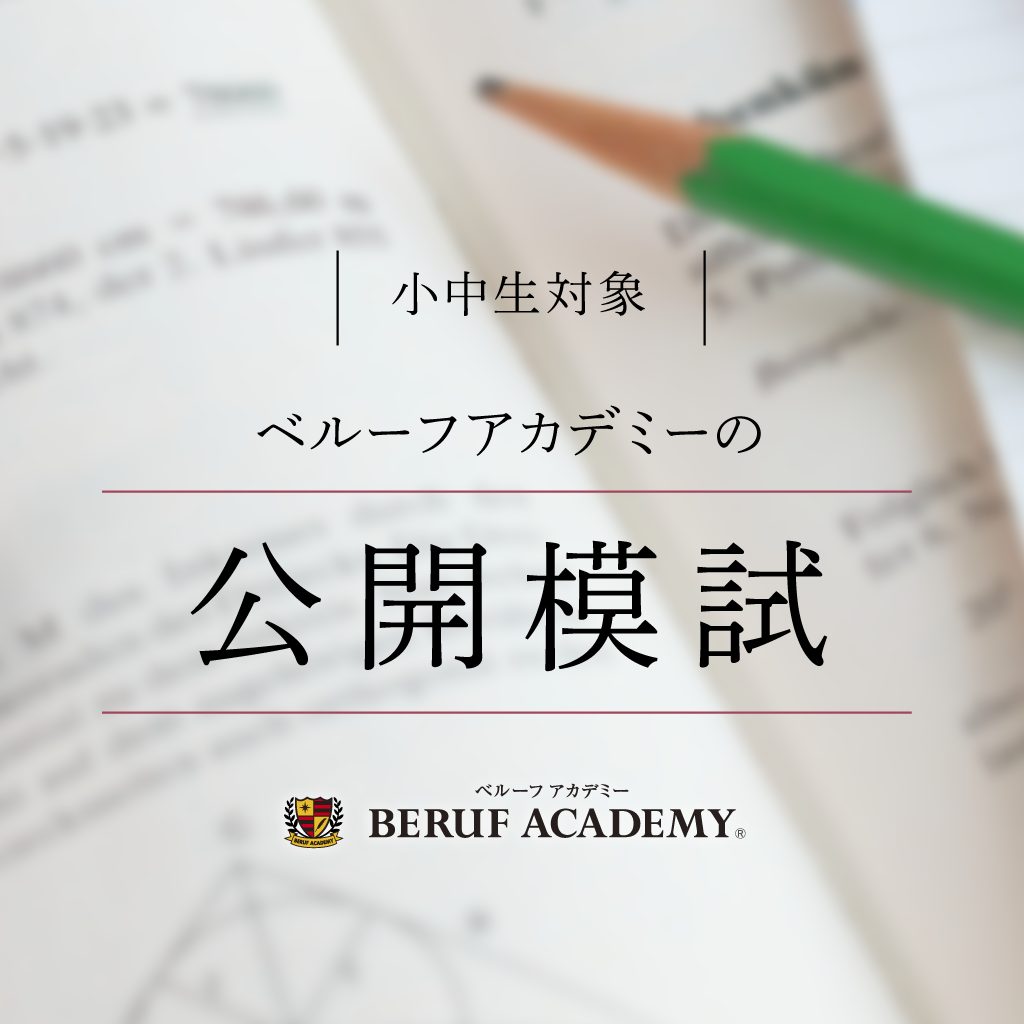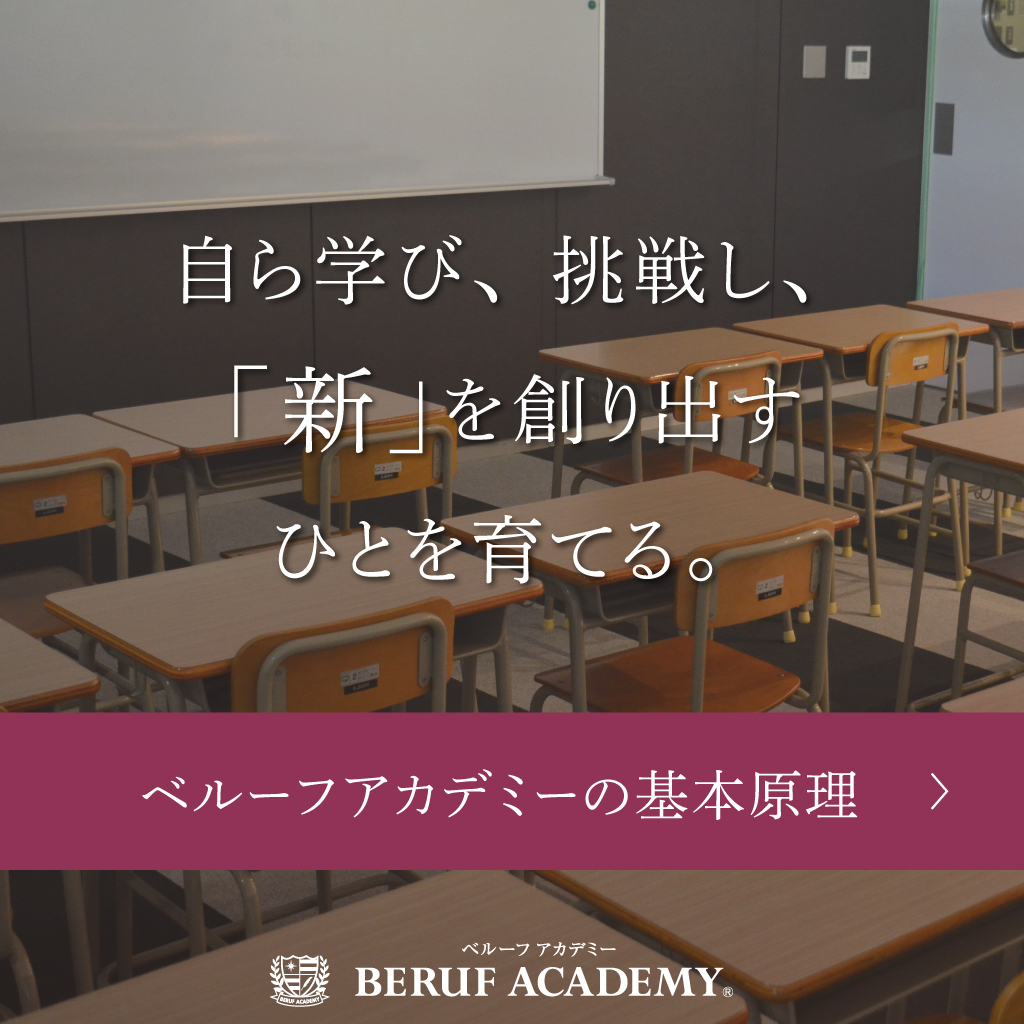2025年度 高校入試解答解説

国語
出題形式と配点
| 大問 | 出題内容 | 知識問題 【配点】 |
選択 【配点】 |
抜き出し 【配点】 |
記述 【配点】 |
合計 【配点】 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論説文 | 6問 | 6点 | 3問 | 7点 | 2問 | 6点 | 2問 | 12点 | 13問 | 31点 |
| 2 | 国語表現 | 3問 | 9点 | 1問 | 3点 | 1問 | 6点 | 5問 | 18点 | ||
| 3 | 漢字 | 3問 | 9点 | 3問 | 9点 | ||||||
| 4 | 古文 | 3問 | 2点 | 2問 | 4点 | 1問 | 2点 | 2問 | 8点 | 8問 | 18点 |
| 5 | 小説 | 1問 | 3点 | 4問 | 9点 | 1問 | 4点 | 1問 | 8点 | 7問 | 24点 |
| 合計 | 13問 | 22点 | 12問 | 29点 | 5問 | 15点 | 6問 | 34点 | 36問 | 100点 | |
問題の傾向と内容
大問は例年通り論説文、国語表現、漢字、古文、小説という5問の構成でした。総問題数は、昨年同様36問、記述の分量、内容は大きく変更ありません。その中で60字程度の記述が2問、35~40字以内の記述が2問、字数制限のない記述が2問、計6問出題されました。
昨年度の問題では60字程度の記述が3問、30字程度の記述が2問だったため、総合的にみると昨年度と変わりありません。傾向に大きな変化はありませんが、漢詩の形式を問う問題は初めて出題され、近年出題されていた言葉や漢字にまつわる問題がありませんでした。記述問題に慣れている生徒にとってはそれほど難しいものではなく、例年通りか若干易化したと考えられます。
- 【大問1】論説文 大嶋仁「1日10分の哲学」より出題
- フランスの哲学者、アンリ・ベルクソンの「時間は量ではなく質であり、意識の中で捉える時間が本当の時間」という哲学思想に関する文章です。漢字の読み、接続語、抜き出し、筆者の意見の説明、本文の構成の工夫、筆者の意見について具体例を用いて説明するなどほぼ例年通りの傾向でした。毎年出題されていた文法は問4で出題されています。
大問1で特筆すべき問題は(6)です。近年この傾向の問題が出題されていますが、全国的にみても類題がありません。論説文を読むときに、具体例と筆者の意見を分けて考え、筆者が具体例を通して何を伝えようとしているか考えながら読むようにしましょう。
- 【大問2】国語表現 語彙に関するクラス内の話し合い
- 本来とは異なる意味で使われることがある言葉について話し合う場面で、2つの話し合いとメモから問題が出題されています。生徒の発言や話し合いの流れについて適切なものを選択、抜き出し、話し合いで使われたメモを完成させるなど例年通りの傾向です。記述問題はメモを完成させるものですが、二回目の話し合いの流れをつかんでいれば決して難しくありません。
大問2で特筆すべき問題は(1)です。発言が果たす役割、説明に関する問題は近年毎年出題されています。今年は適切なものを選ぶというシンプルな選択問題だったのでより解きやすかったと思います。
- 【大問3】漢字
- 誤って使われている漢字を探し、同じ読みの漢字で正す問題です。
階挙⇒快挙、痛まないように⇒傷まないように、観側船⇒観測船
漢字の意味や言葉の意味にも着目し、同音異字、同訓異字について普段から力を入れて学習していきましょう。
- 【大問4】古文・漢詩 「無明草子」、袁凱「京師得家書」より
- 古文と漢文の書き下し文、2つの文章を元に出題されています。「無明草子」は『源氏物語』『伊勢物語』など文学作品を中心に評論した一冊で、その中から文(手紙)のすばらしさについて述べた箇所です。袁凱は元~明時代の政治家、詩人です。家族からの手紙は簡素だが、早く帰ってきてほしいという想いが切実に伝わり、袁凱自身の帰郷への想いが膨らんだという漢詩です。現代仮名遣い、内容に関する記述、2つの文章を読み比べたあとの生徒の話し合いを完成させるといった問題は例年通りでした。今年は漢詩の形式を問われ、「律詩」か「絶句」か悩んだ人もいたのではないでしょうか。
大問4で特筆すべき問題は(5)です。特にⅱの記述問題は、漢詩の内容を正確に理解している必要があります。毎年内容読解にまつわる記述問題が出題されるのが長野県の入試の特徴です。今年はそれほど難しいものではなく、古文・漢文の記述対策をしてきた受験生には解きやすい内容だったでしょう。
- 【大問5】小説 砥上裕將「一線の湖」
- 水墨画の巨匠に弟子入りした主人公が、事故のために思うように描けなくなったことから水墨画を諦めようと悩んでいるとき、姉弟子に神社へ連れ出されたという場面から出題されています。表現に関する問題、ストーリーの流れに関する問題、登場人物の心情の記述など例年通りの問題です。近年出題されていた四字熟語、慣用句の問題、熟語の構成のような漢字にまつわる問題は出題されませんでした。
大問5で特筆すべき問題は(6)です。毎年出題されている心情の記述問題ですが、近年出題されていた「関係すると思われる部分から読み取ったことを付せんにまとめ、それを踏まえて書く」ものではなく、4つのキーワードを使用して書く問題でした。本文のどの部分を参考にして書けばいいか分かっても、それをまとめるのに時間がかかる問題でした。50~70字以内と字数の範囲が広く設定されており、解答例から様々な表現が許容されていることが分かります。
対策
国語は中2から対策ができる唯一の教科です。長野県の国語の問題は全国的に見ても、難易度が比較的高く、特に記述問題、古文・漢文は早めの対策が必須となります。まずは学校で配布される入試対策用の問題集に取り組みましょう。そして記述問題は必ず学校や塾の先生に採点を頼み、記述の精度をあげましょう。古文独特の表現に慣れるために様々な問題に触れる必要があります。中3の2学期以降は長野県の過去問に取り組み、それから全国の過去問題集に取り組むのがベストです。また、長野県の傾向問題に慣れるために学校のテストだけでなく外部の模試を受けることをお勧めします。
数学
出題形式と配点
| 大問 | 出題内容 | 基本 【配点】 |
記述・作図 【配点】 |
応用 【配点】 |
合計 【配点】 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本計算・図形(求角・作図)・確率 | 11問 | 33点 | 1問 | 3点 | 12問 | 36点 | ||
| 2 | データの活用・式による説明・空間図形 | 5問 | 13点 | 1問 | 4点 | 1問 | 3点 | 7問 | 20点 |
| 3 | Ⅰ:一次関数の利用 Ⅱ:放物線 | 6問 | 12点 | 2問 | 6点 | 2問 | 6点 | 10問 | 24点 |
| 4 | 平面図形 | 3問 | 7点 | 1問 | 4点 | 3問 | 9点 | 7問 | 20点 |
| 合計 | 25問 | 36点 | 5問 | 17点 | 6問 | 18点 | 36問 | 100点 | |
問題の傾向と内容
令和7年度の数学入試は、昨年度(令和6年度)と比較して問題数、配点、難易度に大きな変更は見られませんでした。例年通り、基本問題の配点割合が高く、全体的な難易度は昨年度と同程度、もしくはやや易化したと考えられます。文章や情報量が多く、必要な情報を的確に見極めて処理する力が求められました。問題文の読解力や適切な計算スピードが鍵となる試験であったといえます。出題傾向についても顕著な変化はなく、過去の傾向に沿った内容が中心となりました。総じて、安定した出題形式が維持されており、例年と大きな違いは見られませんでした。
- 【大問1】基本計算・図形(求角・作図)・確率
- 問題数、傾向に大きな変更はなく、配点も12問×3点の36点と昨年同様です。内容は基本計算、作図、求角、確率、関数などが出題されました。中1から中3までの広い範囲から問題が出題されており、幅広い基礎知識が求められる構成となっていました。(10)の作図問題は2021年度とほぼ同じ内容でした。
- 【大問2】データの活用・式による説明・空間図形
- 例年と傾向の変化はなく、Ⅰ箱ひげ図とデータの活用〈8点〉、Ⅱ式による説明〈6点〉、Ⅲ空間図形〈6点〉の3問構成でした。Ⅰの箱ひげ図とデータの活用は基本問題ではありますが中央値・範囲・四分位数の用語とその意味をしっかりと理解していないと解くことができない問題です。Ⅱの式による説明は定番の問題パターンからの出題でした。Ⅲの空間図形はⅠやⅡと比べると少し難易度が高く、空間図形の理解が問われる問題でした。
- 【大問3】Ⅰ:一次関数の利用 Ⅱ:放物線
- Ⅰは一次関数の利用と例年通りで13点、Ⅱは昨年の反比例から変わり、2次関数のグラフで11点の出題でした。Ⅰは2018年度長野県入試の問3のⅠとほぼ同様の内容の問題でした。テーマは温度変化で与えられた情報から必要な数値を読み取り、傾きや式を求めるなど論理的に考える力が必要でした。Ⅰ(3)では定番ではありますが、1つの解答を複数の方法で求める記述問題が出題されました。Ⅱは2次関数の変化やx座標が指定されたときのy座標の求め方や座標を文字で表すことなど、座標平面での基本的な操作が問われる問題でした。
- 【大問4】平面図形
- 問題数、傾向について大きな変更はなく、定番の数学の作図ソフトを使った平面図形に関する出題となりました。作図ソフトを使用して図形の拡大縮小、回転移動するという条件は3年連続の出題です。 問4は例年難易度が高く、証明の記述問題もあるため時間のかかる問です。今年も例年同様難易度の高い問でした。 (1)の平行四辺形になるための条件は2021年度以降出題がなかった問題でした。毎年必ず出題される証明問題は今年も相似の証明で、難易度も例年通りでした。Ⅱ(2)(3)は難易度が高く、差がつく問題が出題されました。
対策
大問1は試験全体の約3分の1の配点を占めるため、確実に得点することが重要です。内容は教科書レベルの基本問題が中心のため、素早く正確に解く力が求められます。類題が出題される傾向があり、過去問の問1を解くことや、他の都道府県の入試の問1を練習することも効果的です。
大問2は様々な単元から2~3単元が出題されます。特に連立方程式の利用、規則性、文字式による説明、資料の整理、データの分析、空間図形からの出題が多い問です。これらの単元のどれが出題されても対応できるように対策する必要があります。式の立て方や公式の使い方、解法などをしっかりと身につけて、苦手な単元があれば1つ1つ確実に出来るようにすることが大切です。
大問3は関数の出題が続いています。特に「一次関数の利用」、「二次関数」は頻出です。一次関数の利用は身近なテーマ(料金、速さと時間、水そう)が出題されます。複数のグラフの交点や座標が何を表しているか、またそれぞれのグラフの式を求めることができる力が必要です。全体的に文章量や情報量が多い傾向で、必要な情報だけを読み取る力が必要。二次関数はy=ax2のaの値の求め方、座標平面上の三角形の面積、等積変形の利用など関数や座標の扱いに慣れている必要があります。どちらの問題も長野県だけではなく他の都道府県の入試でも頻出のため、様々な問題に触れて情報の読み取りや立式に慣れて、解ける力をつけましょう。
大問4に出題されるような平面図形は慣れが必要です。まずは中2で学習する「三角形・四角形」、中3で学習する「円周角」、「相似」、「三平方の定理」などの基本が出来ることが重要。その上でこれらが複合した問題を演習する必要があります。しかし相似や三平方の定理は中3の2~3学期で学習する単元のため、対策がどうしても最後になってしまいます。学習してから入試までの期間が短いため、短期間で応用問題に対応できる力を身につける必要があります。可能な限り中3の12月までに三平方の定理まで学習を終わらせて、入試直前の冬休みには長野県の過去問などを利用して平面図形の対策に入りましょう。
英語
出題形式と配点
| 大問 | 出題内容 | 記号 【配点】 |
記述 【配点】 |
合計 【配点】 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リスニング | 8問 | 17点 | 1問 | 3点 | 9問 | 20点 |
| 2 | 単語・文法問題(対話文・グラフ) | 5問 | 15点 | 4問 | 14点 | 9問 | 29点 |
| 3 | 中文読解・条件付き英作文 | 6問 | 16点 | 4問 | 12点 | 10問 | 28点 |
| 4 | 長文読解 | 6問 | 16点 | 4問 | 12点 | 10問 | 28点 |
| 合計 | 23問 | 59点 | 12問 | 41点 | 35問 | 100点 | |
問題の傾向と内容
昨年度(R6年度)と同様4つの大問で構成されており、出題傾向に大きな変更は見られませんでした。問題形式別での配点は、記号問題が59点、記述問題が41点でした。昨年度は、記号問題が66点、記述問題は34点だったため記述問題がやや増えましたが、これは例年並みに戻ったといえます。大問3以外は比較的解きやすい問題で、難易度は昨年度と変わりありません。新指導要領である『現在完了進行形』『原形不定詞』『仮定法』は本年度も扱いはありませんでしたが、文法問題からの出題は問2Ⅰのみとなっており、主に短文~長文の内容理解、読解問題を中心に構成されています。標準的な受験生の英文を読解できるスピードは1分間に50~70語程度と言われていますが、問2~問4を40分間で解くことを考えると全体の英文量は非常に多いです。ペース配分を間違えず、最後まで焦らずに取り組めたかが得点に大きく関わるでしょう。
- 【大問1】リスニング
- (1)はイラスト問題、(2)は対話文、ラジオを聞き、質問に答える問題、(3)は130語程度のインタビューを聞き、正しいメモを選ぶ問題、(4)は70語程度の留守番電話のメッセージを聞き、メモを完成させる問題でした。(1)では、放送が一度しか流れない「一度読み」が定番となってきています。(2)の対話文は昨年度に比べると英文が短かったため、解きやすかったかもしれません。
一方(3)は、昨年度から+30語程度と英文が長くなりました。(4)は一昨年度から出題されている適語補充の問題でしたが、聞き取ることができれば比較的簡単に答えられる問題となっています。リスニング問題のコツは、英文が読まれる前に問題を「先読み」して情報を把握することです。また、2回英文が読まれるものについては、1回目の解答を2回目で「再確認」できるようにしましょう。
- 【大問2】単語・文法問題(対話文・グラフ、ポスターの読み取り)
- Ⅰは適語選択、不足している語句を補って英文を完成させる問題、適切な表現に書き直す問題でした。単語および文法の知識が問われる問題で、毎年正答率が低い傾向にあります。出題されたのは接続詞、未来形、疑問詞、過去形と中2までに習う文法ですが、中3で習う関係代名詞に関する問題も出題されました。また、「禁止する」「誘う」といった重要表現を記述できるかが問われました。解答がひとつに定まらない問題です。自由度が高い分、複数の表現を身につけておきたいです。
Ⅱは、⑴音楽ホールの月別来場者数についてのグラフ、⑵英語で書かれたレストランの案内板を見て、適切な記号を選ぶ問題でした。⑵では選択肢を2つ選ぶ必要がありました。2つ目を選ぶには、レストランの開店時間の情報から、店が閉まっている時間帯を把握できたかが鍵となります。英文に直接書かれていないことまで読み取る必要があるため、解くのに時間がかかったかもしれません。
- 【大問3】短文~中文読解・条件付き英作文
- 「和紙」の性質や良さについて書かれた100~180字程度の文を3つ読み、それぞれ1~3問の問題に答える形式でした。短文ごとに問題が設定されているので、長文が苦手な生徒にとっても取り掛かりやすいでしょう。ただし、昨年は英作文以外が全て記号問題だったのに対し、メモの空欄に適切な単語を書く問題が出題されました。書き始めの文字ヒントがなく、文中から抜き出す問題でもなかったため、やや苦戦する問題といえます。他にも、〈最も伝えたいことを選ぶ〉〈記事にふさわしいタイトルを選ぶ〉といったように、一部の語句や文からの出題ではなく、文章全体の内容からの出題が中心なので、全文を短時間で読み、要点を掴む必要がありました。
その中でも(4)は、昨年も出題された事実と考えを見分けるもので、得点源としたい問題。恒例となった英作文は、提示された2つのアイデアのうち、どちらが良いか理由も含め20語程度で書く問題でした。難しい単語を使う必要はなく、基本的な文法を正しく使えるか、単語を正しいスペルで書けるかがポイントです。受験生のなかでは大きく得点差がつく問題なので、普段から練習と対策をしていきたいですね。
- 【大問4】長文読解
- 昨年度までは人物に関係する問題が出題されましたが、本年はマングローブに関連する地球環境がテーマとなっていました。文章量は400字程度と昨年よりやや増えましたが、テーマ自体はよくあるもののため抵抗なく取り組めたと思います。適語補充の問題は、接続詞、熟語の知識が必要でしたが、決して難しくありません。記述式の適語補充問題も書き出しの文字が指定されていることが大きなヒントとなりました。
〈レポートの内容に合うものを選ぶ問題〉、〈レポートのタイトルをつける問題〉は、文章全体の内容を正しく理解する必要があります。ただ、出題傾向は例年通りのため、焦らずに取り組むことができれば十分得点できる問題が多かったと思います。大問4までにどのくらい試験時間が残せていたか(ペース配分)が、得点差につながると予想されます。
対策
英語の試験では、序盤に時間をかけすぎて最後まで解ききれなかったり、焦ってしまって簡単な問題でも得点を落としてしまったりといった生徒が非常に多いです。これから受験を迎える生徒の皆さんは、中3の夏までに、基礎的な文法や単語力を身につけ、少しでも早めに長文対策に取り組めるようにしましょう。まずは、じっくりと英文と向き合い、内容理解に心がけましょう。そして少しずつ「解くスピード」を意識して学習に取り組んでください。
また、近年学校では、互いの考えや気持ちを伝えあう対話的な学習が重視されています。それに伴い、自分の考えや、簡単な語句を使って英語で表現できる生徒が増えてきているとされています。長野県の入試でも英作文の配点は非常に高いです。受験生になる皆さんも、英語を「読んで解く」だけでなく、「聞く」「書く」「話す」といった機会をぜひ大切にしていってください。
理科
出題形式と配点
| 大問 | 出題内容 | 選択問題 【配点】 |
計算問題 【配点】 |
記述問題 【配点】 |
その他 【配点】 |
合計 【配点】 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物 | 6問 | 16点 | 1問 | 3点 | 1問 | 3点 | 1問 | 3点 | 9問 | 25点 |
| 2 | 化学 | 2問 | 5点 | 4問 | 12点 | 1問 | 3点 | 2問 | 5点 | 9問 | 25点 |
| 3 | 地学 | 5問 | 12点 | 2問 | 4点 | 2問 | 6点 | 1問 | 3点 | 10問 | 25点 |
| 4 | 物理 | 1問 | 2点 | 3問 | 8点 | 4問 | 11点 | 2問 | 4点 | 10問 | 25点 |
| 合計 | 14問 | 35点 | 10問 | 27点 | 8問 | 26点 | 6問 | 15点 | 38問 | 100点 | |
問題の傾向と内容
大問は例年通り4問の構成で、生物・化学・地学・物理分野から1問ずつ出題されました。また、それぞれの分野からテーマが2題ずつ出題されています。本年度は昨年度(令和6年度)に比べ計算問題が多く、また選択問題でも「すべて選びなさい」形式の出題があり、昨年に比べると難しいと感じた生徒も多かったと思います。ただし、昨年度の問題が例年に比べ計算問題が少なかったため、難易度としては例年通りに戻ったか、計算が苦手な生徒にとっては難易度が高いように感じられたと思います。
- 【大問1】ツユクサの蒸散・ヒキガエルの発生
- Ⅰでは蒸散にかかる基本的な知識を問う問題から、記述問題、やや難易度が高い計算問題が出題されました。Ⅱではヒキガエルの発生をもとに有性生殖に関わる問題が出題されました。
特筆すべき問題としてはⅠの⑷が挙げられます。蒸散量を求める問題は頻出で、対策できた生徒も多かったと思いますが、全体に対する葉の裏の気孔の数の割合を求める問題となるとやや難易度が高い問題でした。
- 【大問2】プラスチックと密度・酸化銀の分解
- Ⅰではプラスチックと密度に関する問題が出題されました。ここでは表やグラフの読み取り、計算問題が出題されました。Ⅱでは酸化銀の熱分解に関する問題が出題。オーソドックスな問題構成だったため、計算問題一部を除いて、得点源にしておきたいところです。
大問2では計3つの計算問題が出題されました。そこまで難易度が高くない計算でしたので、落ち着いて考えれば解ける問題です。計算問題は敬遠されがちですが、基本的な計算問題から慣れていきましょう。
- 【大問3】火山と地層・金星の観察
- Ⅰでは火山灰が降り積もった地層を調査したことに関する問題が出題。また火山灰に絡めて、天気(今回は偏西風)に関する知識を問う問題が単元を横断するように出題されました。Ⅱでは金星の満ち欠けに関する問題が出題。一部計算問題を除いてはオーソドックスな出題に感じました。
確実に取れるようにしたいのが、Ⅱの⑵です。天体分野では金星の満ち欠けを習うのが中3の2学期末から3学期初めであるため、習ったものを深く掘り下げないまま受験に向かう生徒も多くいます。天体まではできる限り予習で早めに終わらせ、復習に取り掛かりたいところです。
- 【大問4】回路とモーターに流れる電流・滑車を用いた実験
- Ⅰでは回路からの出題で、学校問題集を解くだけではなかなか触れることができないタイプの出題パターンでした。並列回路では抵抗を扱ったとしても2つまででしたが、今回は条件によっては3つの抵抗を持つ並列回路となり、どうやって解いたらいいのか分からなくなる生徒も多くいたかと思います。Ⅱでは仕事の原理と動滑車についての問題が出題されました。4問出題されましたが、先にある3問が4問目を解く上での導入となっており、問題のつながりを感じられる出題でした。
Ⅱの⑷の問題では、動滑車に関する知識を知っていれば即解ける問題でありました。が、実際は動滑車が2つよりも多く用いる問題に出会うことはなかなかないため、設問中の表やこれまで解いた問題をヒントに考える必要がありました。
対策
計算問題が昨年より多く出題されたと述べましたが、実際は例年並みとも言えます。計算問題と聞くと敬遠してしまう生徒もいるかと思います。しかし、長野県の計算問題はそこまで難易度が高いわけではないため、公式に基づいた計算ができることで、正答にたどり着けることが多いです。ただし、式を立てるために、問題の条件や表・グラフの読み取りが必要となります。
これから受験を迎える生徒の皆さんにお伝えしたいのは、解く速さを追い求めるよりも、正確に読み取ることを重点に置いて問題を解いてほしい、ということです。長野県の入試は問題の条件や設問をきちんと読み取ってしまえば、そこまで難しい解法にならない問題が多いです。
解く速さは後からついてきますので、まずは書いてあることを正確に読み切ることを一つの訓練にしてみましょう。
社会
出題形式と配点
| 大問 | 出題内容 | 語句記述 【配点】 |
選択・数字 【配点】 |
記述論述 【配点】 |
合計 【配点】 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歴史分野 | 1問 | 2点 | 9問 | 25点 | 1問 | 3点 | 11問 | 30点 |
| 2 | 地理分野 | 4問 | 9点 | 6問 | 15点 | 4問 | 12点 | 14問 | 36点 |
| 3 | 公民分野 | 2問 | 4点 | 7問 | 18点 | 3問 | 12点 | 12問 | 34点 |
| 合計 | 7問 | 15点 | 22問 | 58点 | 8問 | 27点 | 37問 | 100点 | |
問題の傾向と内容
今年度は記述論述問題が昨年度に比べて出題数は変わりませんでしたが、配点が2点少なくなりました。語句記述問題の配点が9点減り、選択・数字問題が10点ほど高い配点となりました。資料の空欄補充を選択肢から選ぶ問題が中心の構成となっています。問題自体はより基礎的なものが多く、問題集や過去問で触れることのできる問題がほとんどでした。税や選挙、地域おこしや外国人旅行者など、受験生に興味関心を持って取り組んでほしい事柄が多く扱われているように考えます。
難易度としては決して高くなく、やや易しめといえます。基礎知識の定着を図り、過去問から傾向がつかめていれば着実に得点できる問題がほとんどです。
- 【大問1】歴史分野
- 〇テーマ 税の制度にかかわる各時代の特徴について知識を問う問題
〇出題構成
昨年度同様に問1での出題となりました。語句記述問題が1問出題されました。選択・数字問題は9問で25点分と、昨年度に比べ問題数は1問増え、配点が2点ほど多くなりました。複数選択問題は2問から1問に減りました。記述問題の数・配点は昨年と同様に1問、3点の出題となりました。
〇問題構成
単語知識を問う問題の出題が昨年と同様の1問ずつの出題となりました。選択問題では、すべて正しい情報を選択させる問題で、この構成自体は昨年から大きな変化は見られません。複数選択問題は1問出題されており、【問1-(2)②】、昨年より1問少なくなっています。時代の並べ替え問題は2問から1問に減りました。略地図を用いた問題は昨年同様1問出題されましたが、略年表の資料を用いた問題は出題がありませんでした。また資料の中の空欄補充の選択問題が中心の出題形式となっています。
昨年度はなかった時代の並び替え問題が出題され、複数選択問題が少なくなりました。昨年度よりも資料の読み取りに加えて知識を問う問題が多くなりました。各時代の出来事、制度、特徴を正確にとらえておく必要があります。また起こった出来事がどの都市や国で起こった出来事なのかを確認しておきましょう。
- 【大問2】地理分野
- 〇テーマ 梅の加工販売をテーマとした日本の地形や流通、輸送の特徴(日本地理)とサウジアラビアの貿易、農業、エネルギーについて(世界地理)
〇出題構成
昨年度同様に問2での出題となりました。語句記述問題の数は昨年より2問減り、配点は5点減少しました。昨年度同様そのうち1問は完答問題、また漢字指定が1問出題されています。また字数指定、語句指定のある問題が3問出題されています。選択・数字問題は2問増え、配点は4点増加しました。複数選択問題は昨年度から1問減り、1問出題されています。記述問題の数・配点はそれぞれ1問、4点昨年より増えています。今年度は地理分野での記述問題の出題が一番多くなりました。
〇問題構成
今年度の地理でも昨年度同様、複数の資料がちりばめられていますが、資料には略地図、地形図、図、グラフ、会話文など多くのパターンが見られ、歴史と同様に空欄補充の問題が中心の出題形式となっています。様々な資料に触れておくことが大切です。知識を問う問題もありますが、出題されていることは、多くの問題集や過去問で扱われているものがほとんどです。受験生の皆さんは、なるべく過去の問題に早く、多く触れ、問題や資料の配置、問題傾向に慣れていくことが入試対策に大切と考えます。定番の記述問題を繰り返し解き、基礎知識の定着に励みましょう。
- 【大問3】公民分野
- 〇テーマ 持続可能な社会をテーマにした資料の読み取りと基礎知識を問う問題
〇出題構成
昨年度に比べ、公民分野の配点が2点減りました。記述問題が1問減り、配点は3点減少しています。語句記述問題と選択数字問題の出題の数はそれぞれ1問減って、2問増え、配点は語句記述問題が3点減り、選択数字問題の配点は4点増えました。複数選択問題の出題はありませんでした。また誤っているものを答える問題はなく、すべて適切なものを選ぶ問題でした。
〇問題構成
昨年度同様、問3に公民分野と論述問題が組み合わされて出題されました。記述問題は公民分野で2問減少しています。今年度の特徴としては国の政治分野での出題がなく、外国人旅行者や地方自治についてなど地域の問題を中心に基礎知識を問う出題がほとんどでした。論述問題については4つの資料から読み取れることについて触れて、理由と課題について各問題が出題されています。昨年度と同様に理由と課題についてそれぞれ2つずつ選ぶこと、またすべての資料を必ず1回は選ぶことという条件がついています。論述問題のテーマは人口減少と高齢化における公共交通の利便性という身近な課題となっています。昨年度同様、公民の問題では、問題を通じて、受験生の皆さんに意識してほしい社会問題が取り上げられています。そのため、教科書の知識に限らず、ニュースなどを通じて、社会で話題になっている事柄、自身の生活する地域をより良くしていくことについて興味関心を広げていくことが、入試対策として大切になります。
対策
総評でも触れたとおり、基礎知識の定着を図り、出題の傾向をつかむために問題集を繰り返し解き、過去問に早く、何度も取り組みましょう。難問といえるような問題はないため、ケアレスミスが大きく結果に響いてしまう可能性があります。取りこぼしがないよう1問1問丁寧に取り組み、見直しができるよう時間配分にも気を配りましょう。
記述問題についても資料から読み取れる要点を短い言葉で簡潔に言い表す練習を繰り返しましょう。また字数制限や字数指定のある問題が増加傾向にあります。10字程度、50字程度、80字程度の記述問題に多く触れられるよう学校や塾の先生に相談し、採点も自己採点ではなくほかの人にお願いして精度を高めていきましょう。
そして、皆さんの身の周りの問題をどのように解決すればよいのか?という、社会全体に目を向けさせる傾向は変わることはないと思われます。是非、身の回りのニュースや出来事に関心を持ち、お友達や周りの大人と話をしてみてください。
中学部のコース詳細はこちら